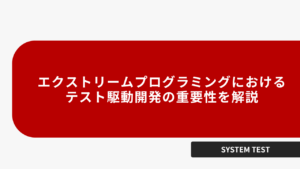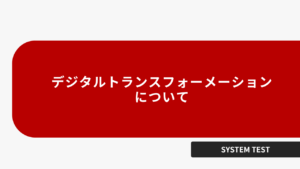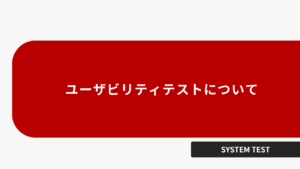モンキーテストについて
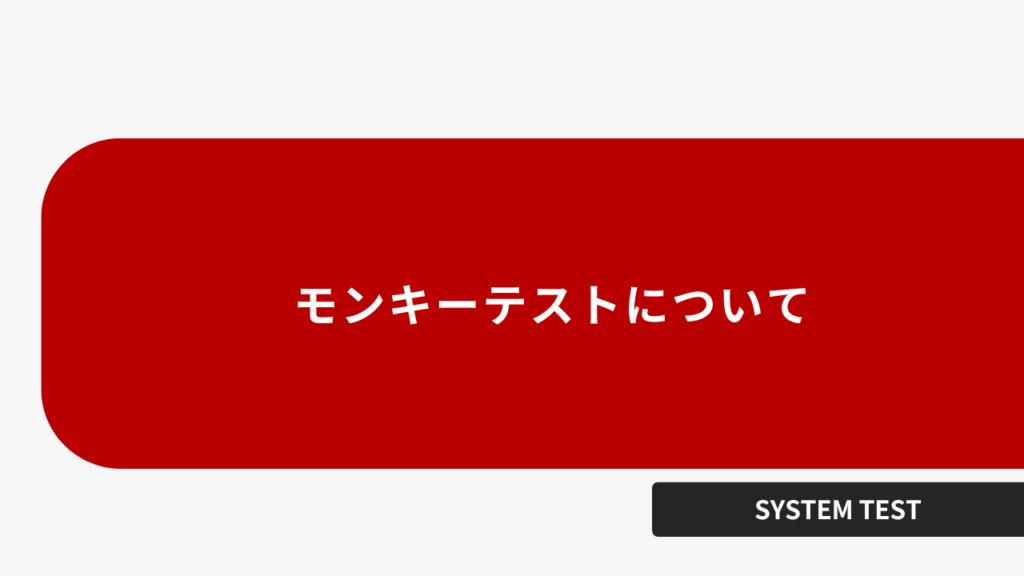
モンキーテストとは
モンキーテストとは、仕様書や操作手順にとらわれず、あえてランダムに操作することでソフトウェアの不具合を見つけるテスト手法です。
例えば、スマートフォンアプリのテストで、ユーザーがひたすら画面を連打したり、画面外をスワイプしたり、無意味な文字列を入力したりするなど、普通では想定しない使い方を試すことで、予期しないバグやクラッシュを発見できます。
この「モンキー」という名前は、1980年代にAppleが開発した「The Monkey」というツールに由来しています。
このツールは、MacアプリケーションのUIを無作為にクリック・入力して動作確認を行うもので、「サルが適当に操作しているようなテスト」というイメージから名付けられました。
現在では、主にユーザーインターフェース(UI)の安定性をチェックしたり、ランダム操作に対する耐性を確認したりする目的で活用されています。
他のテスト手法との違い
モンキーテストと混同されがちな手法に「アドホックテスト」や「探索的テスト」があります。
違いを理解することは、それぞれを適切に使い分けるうえで重要です。
アドホックテストとの違い
アドホックテストは、事前の計画なしにテスターの勘や経験に基づいて自由に操作を行う点でモンキーテストと似ています。
ただし、テスターは「バグが出そうな操作」や「過去の不具合履歴」などをもとに、ある程度の狙いを持ってテストを行います。
探索的テストとの違い
探索的テストは、仕様書を読みながら実際に手を動かして理解を深め、テストの設計と実行を同時に進めていくスタイルです。
経験豊富なテスターが、学習しながら柔軟にアプローチを変える点が特徴です。
一方、モンキーテストは操作が完全に無作為であるため、知識や経験がなくても実施可能です。
まったく前提知識のない人、あるいは実際のユーザー視点に近い第三者が操作することで、思いもよらないバグを検出できる可能性があります
モンキーテストのメリット
モンキーテストは“誰でも実行できるシンプルなテスト”でありながら、想定外のバグの発見、初期段階での柔軟な運用、ユーザー視点のバグ発見、自動化による効率化など、多面的なメリットを持ったテスト手法です。
以下では、モンキーテストのメリットについて紹介していきます。
想定外のバグが見つかる
モンキーテストの最大の魅力は、通常のテスト設計では見逃されがちな「想定外のバグ」を偶然に発見できる点です。
仕様書に沿った操作や決まった手順で行うテストでは、ユーザーが実際にどのような使い方をするかまでは想定しきれません。
しかし、モンキーテストではあえて仕様を無視した無作為な操作を行うことで、開発者が思いもよらないバグやクラッシュを発見することが可能になります。
たとえば、入力フォームに10,000文字以上の長文を貼り付けたときや、ボタンを1秒間に10回以上連打したときなど、想定外の動作によって画面がフリーズしたりアプリが強制終了したりする事例があります。
実際、あるECアプリでは、購入画面で「戻る」ボタンを素早く連打したことで二重決済エラーが発生し、そのバグはモンキーテスト中に偶然発見されたものでした。
このような“計画外のバグ”を表に出すためのテストとして、モンキーテストは非常に有効です。
導入しやすく、誰でもできる
モンキーテストのもう一つの大きな利点は、事前準備や専門知識がほとんど不要であるという点です。
テスト仕様書の作成やテストケースの設計を待たずに、UIがある程度完成していればすぐに始めることができます。
たとえば、まだ仕様書が固まっていないプロトタイプ開発の段階でも、「とりあえず動作確認をしたい」という目的で気軽に活用できます。
また、開発メンバー以外でも参加しやすいのが特徴です。営業担当やカスタマーサポート、新人メンバー、あるいは外部の第三者でも、アプリを自由に操作して不具合を見つけることができるため、視点の偏りを防ぎやすくなります。
むしろ製品に詳しくない人のほうが、ユーザーの“うっかり”に近い行動を取りやすく、結果として有益なバグ発見につながることも少なくありません。
こうした「誰でもできる」手軽さが、モンキーテストの導入のしやすさに直結しています。
ユーザー視点のバグが発見できるということもモンキーテストのメリットのひとつです。一般的に、テストは「決まった手順通りに操作して、正しく動作するかを確認する」というスタイルで進められます。
しかし、実際のユーザーは仕様書通りに操作してくれるとは限らず、間違った順序でボタンを押したり、別の画面に遷移してしまったりと、現場では“予測不能”な使われ方がよく発生します。
モンキーテストでは、こうした実際の利用環境に近い“偶発的な使われ方”を再現できるため、リアルなユーザー視点に立った品質チェックが可能になります。
たとえば、通信環境が不安定な場所でアプリを操作しているとき、操作中に突然通信が切れた場合や、再接続直後に再操作した場合など、通常のテストでは見逃しやすいシナリオでもモンキーテストによってバグが見つかることがあります。
また、複数の操作を短時間に連続して行った際に発生する表示バグや、同時押しによる予期せぬ挙動など、「とっさの操作」に対するアプリの耐性をチェックできる点は、ユーザー体験を高めるうえで非常に重要です。
自動化にも対応できる
モンキーテストは、手動だけでなく自動化との相性が良いという点でも注目されています。
とくにAndroidアプリ開発の現場では、「monkeyコマンド」と呼ばれる専用ツールを使って、何万件ものランダムなUIイベント(タップ、スワイプ、入力など)を自動的に発生させることができます。
これにより、人間では到底実行できないような量の操作パターンを短時間で試すことが可能になります。
たとえば、夜間に自動化されたモンキーテストを数時間走らせて、朝にクラッシュレポートやログをまとめて確認することで、コストを抑えながらバグ検出率を高めることができます。
こうした「テストの空き時間を有効活用する」方法としても、モンキーテストの自動化は非常に有効です。
定期的に実行することで、特定のバージョンや端末に固有の不具合を早期に検出する手段としても活用されており、安定性テストの一環として広く取り入れられています。
モンキーテストのデメリット
上記したように様々なメリットをもつモンキーテストですが、扱う上で覚えておきたいデメリットも存在しています。
以下に挙げるデメリットを把握した上で、他のテストと組み合わせながら、「テスト全体のバランスを取るための補完的手法」として使うのが理想的な活用方法といえます。
再現性が低い
モンキーテストはその名の通り、完全に無作為な操作を繰り返すため、仮にバグが発見されたとしても、「どのような操作でその不具合が起こったのか」を後から特定するのが非常に困難です。
たとえば、ある画面でクラッシュが起きたとしても、タップした順番や操作のタイミング、入力内容などが記録されていなければ、開発者が同じ現象を再現しようとしても失敗することがよくあります。
実際、テスト中に「何か変な動きがあった気がする」「さっき落ちたけど再現できない」ということが頻発すると、発見されたバグが埋もれてしまい、結果的に品質向上につながらない恐れもあります。
このような再現性の低さは、モンキーテストを実施する上での大きな課題であり、操作の様子を録画する、ログを取得する、クラッシュレポートツールと連携するなどの対策が必要です。
網羅性がない
モンキーテストは操作内容が完全にランダムであるため、テスト対象の全機能や重要な操作フローを「確実にカバーする」ことはできません。
たとえば、ユーザー登録から購入完了までの一連の重要な処理フローがあるアプリであっても、モンキーテストの結果、その流れを1回も通らないまま終わってしまう可能性も十分にあります。
このように、製品の核となる機能や主要な画面遷移が検証されないまま、ただ偶発的な動作だけを試すことになると、「バグは見つからなかったが、本当に大丈夫か?」という不安が残ります。
つまり、モンキーテスト単体では品質保証の裏付けができないのです。
特にリリース判定や品質報告など、証拠に基づいた説明が求められる場面では、網羅性のあるスクリプトテストやシナリオテストと組み合わせることが前提となることを覚えておきましょう。
非効率になりやすい
操作を完全に無作為に行うという性質上、同じような操作ばかりが繰り返されたり、意味のない挙動に時間が割かれたりすることがあります。
その結果、「1時間かけてテストをしたのに、結局何もバグが見つからなかった」という非効率な状態に陥ってしまうこともありえます。
特に、テストの実施範囲や目的が曖昧なまま始めてしまうと、得られる情報が乏しく、かえって時間の無駄になってしまう恐れがあります。
例えば、すでに動作が安定している設定画面やヘルプページを延々と操作しても、重大なバグが出る確率は低く、生産性の観点からは効果的とは言えません。
モンキーテストは「何を狙って行うか」を定めにくいため、テスト範囲や対象画面、実施時間をあらかじめ絞り込む工夫が必要です。
また、他のテストが一通り完了した後の「抜け漏れ確認」や「負荷耐性チェック」といった補完的な目的で使うことで、より合理的に活用できるようになります。
モンキーテストの実施ポイント
この部分では前述したメリットとデメリットを踏まえつつ、モンキーテスト実施の際にポイントとなる部分をおさらいもかねて説明していきます。
対象範囲を絞って実施する
モンキーテストは自由な操作が可能なテストですが、すべての画面・機能を無作為に試すと操作が散漫になり、肝心なバグの発見率が下がることがあります。
そのため、事前に「今回はログイン周辺」「購入フローのみ」など、対象範囲をある程度絞っておくことで、意図を持ったテストがしやすくなります。
結果的に、重要な箇所への集中と効率的な検証が可能になります。
ログや記録の仕組みを整える
モンキーテストは再現性が低くなりがちです。バグを見つけたとしても、どのような操作で発生したのかを思い出せないと、修正が難しくなります。
そのため、画面録画や操作ログの取得、クラッシュレポートの自動出力など、あとから確認できる仕組みをあらかじめ整備しておくことが重要です。
複数人でテストする場合には、報告形式や記録方法の共通ルールも決めておくとスムーズです。
イレギュラーな操作を意識的に行う
単なる無作為な操作だけでなく、ユーザーがうっかりやりそうな“変な操作”を意図的に試すことも、モンキーテストでは有効です。
例えば、画面遷移中にスマホの向きを変える、通信を切った状態でボタンを押す、記号や絵文字だけを入力するなど、通常のテストケースでは実施しないような動作を積極的に試してみましょう。
こうした操作の中に、製品の弱点が潜んでいることがあります。
第三者の視点も活かす
モンキーテストは専門知識がなくても実施可能なテスト手法です。
そのため、開発メンバー以外の人、たとえば営業職や新人メンバー、他部署のスタッフなどに協力してもらうと、新鮮な視点での操作が行われ、思わぬバグの発見につながることがあります。
特にプロダクトにあまり詳しくない人ほど、実際のユーザーに近い行動をとる傾向があるため、貴重なフィードバックを得やすくなります。
自動化ツールとの併用を検討する
モンキーテストは手動だけでなく、ツールによる自動化も可能です。
上述したようにAndroidアプリでは、「monkeyコマンド」を使って、数万件ものランダムなUI操作を自動で実行できます。
これにより、人手では到底試しきれないような操作パターンも検証できるようになり、バグの発見率が高まります。
夜間に自動でテストを走らせて、翌朝にクラッシュログを確認するといった運用も現場ではよく行われています。
実施の目的と役割を明確にしておく
モンキーテストは万能なテスト手法ではなく、あくまで補助的な位置づけとして考えることが大切です。
網羅的なテストや仕様に基づいた検証には向いていないため、「想定外の不具合の検出」「操作ミスへの耐性確認」「抜け漏れの最終確認」など、狙いや役割をはっきりさせて活用することで、テスト全体の中での位置づけが明確になり、成果も出しやすくなります。
実施タイミングと活用シーン
モンキーテストは、仕様に沿った網羅的なテストとは異なり、想定外の動作や偶発的なバグを検出するための補完的な手法です。
その特性を活かすには、「いつ」「どんな場面で」実施するかが非常に重要です。
タイミングを誤ると、ただの“無秩序な操作”に終わってしまうため、効果的な実施タイミングを見極めることが求められます。
まず有効なのは、開発の初期段階やUIの仮実装ができあがった直後です。
この段階では、仕様書やテスト設計が整っていないことも多く、計画的なテストを行うのが難しい場合があります。
そんなときに、まずは簡易的に動作確認を行う手段としてモンキーテストを活用することで、画面遷移の不具合やクラッシュといった致命的な問題を早期に洗い出すことができます。
プロトタイプ段階での「ざっくり確認」に向いている手法といえるでしょう。
次に適しているのは、一通りのテストが終わったあとの最終確認フェーズです。
設計に基づいたテストが完了し、「一応全部通ったけど、何か不安が残る」という段階で、あえて予測不能な操作を行うことで、“設計から漏れていたバグ”や“ユーザーの誤操作によるクラッシュ”を発見できる可能性があります。
この段階でのモンキーテストは、まさに「抜け漏れ確認」や「予期せぬ不具合の最終チェック」として機能します。
また、ユーザーに近い操作環境での動作確認をしたいときにも有効です。
たとえば、実機での動作確認や、不慣れな操作をするユーザーの視点を模した検証が必要な場合、非エンジニアのスタッフにモンキーテストを任せることで、実際の利用に近い挙動を検証できます。
ユーザビリティに対する気づきや、操作性の問題にもつながることがあるため、リリース前のチェックとしても有効です。
さらに、長時間稼働や負荷状態に対する耐性を確認したいときにもモンキーテストは使えます。
自動化ツールを使って数千回以上のランダム操作を連続実行し、クラッシュやリソースの異常を検出するようなケースです。
とくにスマートフォンアプリやWebサービスでは、安定稼働の検証として、夜間に自動でモンキーテストを走らせる運用も一般化しています。
このように、モンキーテストは「想定外を想定する」という立場から、さまざまな局面で役立ちます。
計画的なテストではカバーしきれない部分を埋める役割として、開発初期からリリース直前まで、プロジェクトのあらゆるフェーズで柔軟に取り入れることが可能です。
ただし、あくまで補完的な手法であることを意識し、他のテストと組み合わせながら活用することが、効果的な運用につながります。
まとめ
モンキーテストは、無作為な操作を繰り返して想定外のバグを発見するテスト手法です。
仕様に縛られず、誰でも手軽に実施できる一方、バグの再現が難しく、網羅性に欠けるという欠点もあります。
開発初期やテスト完了後の最終確認、ユーザー視点での操作確認など、計画的なテストでは見逃しがちな問題の補完に有効です。
ログ取得や自動化ツールとの併用で精度を高める工夫が重要です。
この記事を書いた人